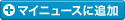多国籍企業ステランティスが擁するイタリアの自動車ブランド、フィアットのAセグメントミニカー『500C』で3700kmあまりツーリングを行う機会があったので、インプレッションをお届けする。
◆ねらいに反して絶大な支持を得たフィアット500
フィアット500は2007年に欧州デビューを果たした全長3.6m級のミニカー。アイデアの源泉は2人乗りのシティコミューター『スマート』に触発される格好で製作され、2004年に発表された3人+1人乗りのコンセプトカー『トレピウーノ』。
そのトレピウーノがシティコミューター的なコンセプトよりも、1957年に登場した同社の歴史的名車『NUOVA 500(チンクエチェント)』をモダナイズしたようなデザインが熱狂的な支持を集めたことから、当時社長だったセルジオ・マルキオンネ氏が若手の懐刀として寵愛していたルカ・デ・メオ氏(現ルノーCEO)をプロジェクトリーダー、初代BMW MINIを手がけたフランク・スティーブンソン氏を設計主任、近年ではフェラーリ初のSUV『プロサングエ』を作出したフランコ・マンツォーニ氏をデザイナーに起用し、超ショートボディではない普通のAセグメントに修正し、500の誕生50周年にあたる2007年に狙いを定めてリリースする計画を急きょ立てた。
こういうアイデア先行型の商品だったため、開発は長期間をかけて練り込むという当時の欧州スタイルではなく、2003年にデビューした同社のミニワゴン、第2世代(初代を前期と後期に分けて考える場合第3世代)『パンダ』のプラットフォームをホイールベースを変えることなく流用するなど、わりと手軽な形で行われた。マルキオンネ氏自身、乾坤一擲の勝負モデルと考えていたわけではなく、遊びゴコロ重視のパイクカー感覚だったとも伝えられる。
ところが500はフィアットの当初の想定と異なり、2007年のデビュー以降Aセグメントのド真ん中のクルマとしてミニカーユーザーから絶大な支持を取り付けた。しかも欧州での販売のピークはデビューから実に10年後の2017年と、初動にありがちな。今も勢いを失っておらず、年によってパンダと首位が入れ替わりながら同カテゴリーで圧倒的なワンツーフィニッシュを続けている。彼の地ではリセールバリューが同クラスのライバルと比較して圧倒的に高いというのも人気が衰えない理由のひとつだ。
欧州ではCO2排出規制に対応するため2020年以降、パワーユニットが1リットル3気筒+パラレルハイブリッドの「ファイアフライ」に一本化されているが、「デュアロジック」というシングルクラッチ式自動変速機が用意されず6速MTのみということもあってか、日本向けには875cc2気筒ターボ「ツインエア」と古典的な1.2リットル4気筒8バルブ自然吸気がデュアロジックとの組み合わせで供給されている。
今回のテストドライブ車両はオープントップモデルの500Cで、パワートレインはツインエア+デュアロジック。ドライブルートは東京〜鹿児島の周遊で総走行距離は3711km。シーズンは盛夏で、最高39度の高温環境であった。
最初に500Cの長所と短所を5つずつ列記してみよう。
■長所
1. 楽しすぎる、面白すぎる、気持ち良すぎる。
2. メーター読み85km/hまで走りながらトップを開閉可能。
3. 意外に後席が広く、4名乗車は結構イケる。狭い荷室もスクエアで意外に使える。
4. 初期型とはまるで異なる1クラッチ自動変速機デュアロジック。
5. エンジンの効率が非常に良い。
■短所
1. 3ドアなので後席へのアクセス性はもちろん悪い。
2. 市街地では自動変速任せにしていると燃費が悪い。
3. タイヤ空気圧センサーなどが時々謎な動きをする。
4. 要求オクタン価が95RONであるため日本ではプレミアムガソリンを必要とする。
5. ADAS(先進運転支援システム)はおろかシティ緊急ブレーキも持たない。
◆単なるセミオープンカーではない!心の底からシビレるクルマ
ではレビューに入っていこう。500Cは心の底からシビレるクルマだった。ドライブ前は500にキャンバストップの開放感を加味したようなものかと想像していたが、いざ乗ってみたら印象は全然違っていた。有体に言えば、オープントップを心ゆくまで味わえるクルマに500のデザイン、走り、実用性を持たせたクルマのように感じられた。
500Cでのオープンエアドライブは本当に気持ちいい。500Cの幌は通常のキャンバストップと異なり、1957年型NUOVA500、あるいはそれをベースとしたアウトビアンキの『ビアンキーナ・トラスフォルマービレ』がそうであったようにリアウインドウまで折り畳めるようになっている。気持ち良いのはその全開モードで、キャンバストップ状態とは別モノ。ほんのちょっとした違いのようだが、室内の明るさは桁違いなうえ、風の室内の吹き抜けも真正オープンカーと変わらない。ドアの窓を開ければもう完璧だ。
もっとも、これだけなら単なるセミオープンカー。500Cの素晴らしい点は、メーター読み85km/hまでなら走行中でも自由に開閉ができることだ。高速道路で排気ガスが充満した長大なトンネルに差しかかるときでも、第1走行車線をのんびり走りながら屋根を閉めれば排気ガスの中を突っ切らなくてもすむ。古いエンジンのディーゼルダンプカーや家畜輸送車などの後ろに付いたときも同様だ。高速を含めあらゆる道路で普通に走りながらトップを自在に開閉できることの特別感は味わってみないとわからないポイントだった。
小型車クラスでこんなオープンエアドライブ可能なクルマは基本的に2人乗りなのだが、500Cは居住区が犠牲になっておらず、4人が無理なく乗ることができる。カーゴスペースも小さいながらもスクエアな設計になっているため、積み方を工夫すれば想像よりずっと多くの荷物を収容できる。加えてクローズドボディの500と同様、走りや乗り心地も意外や意外に優れている。車体は短く形は丸くフェイスはファニーというマルチーズみたいなクルマが自分のためにこんなにも頑張ってくれているのだと思うとついつい嬉しくなってしまう。
言うまでもないことだが、これはあくまで筆者個人の感想。一般的にはオープントップなど不必要という人が多数派だろうし、2ドアボディであることによる実用性の低さ、乗車定員が4人どまりなこと、シティブレーキすらついていないという先進安全・運転支援システムの欠如、日本車と比較すると信頼性が低そうなイメージ等々、さまざまなネガティブ要素がある。
だが、太陽の光を浴びながら、風を感じながら旅をするのが好きという人にとっては、いつでもどこでも走りながら屋根の開閉が可能で、開放感もキャンバストップよりずっとフルオープンに近い500Cはモロにブッ刺さるクルマだろう。南国鹿児島生まれの筆者はまさにそのタイプで、500Cを駆っての3700kmドライブは愉悦そのものだった。
◆オープントップにして走る快楽は麻薬的なものがある
試乗時は真夏で、ドライブ中の気温は最高で39度に達した。が、その時でも2リットルペットボトル飲料を2本常備し、水分と塩分を補給しながら長距離走行だろうとシティライドであろうと見境なく屋根全開で走った。風の吹き抜けが良く、汗などかくそばから蒸散してしまうので、帽子を被る程度で十分に耐えられる。事後に鏡を見て真っ黒に日焼けしているのには少々ビビったが、翌日もまた真夏の快晴の下、遠慮会釈なしにオープンで走った。500Cをオープントップにして走る快楽はそれだけ麻薬的なものがあった。
もちろんそういう嗜好のユーザーは少数派だろうが、潜在的にみれば珍種というほどの少数派でもないように思う。鹿児島で高校同窓生3名で薩摩半島南端をワンデードライブしてみた。潮だまりを熱帯魚が泳ぎ回る長崎鼻、坊ノ岬沖海戦で没した戦艦大和以下第二艦隊の慰霊碑がある平和記念展望台、鑑真和上上陸の地である坊津などを巡る200kmあまりのドライブだった。
同行者にも500Cは大人気。そのうち一人が何と1か月もしないうちにクルマをシチリアオレンジの500Cに買い換えていた。クルマへの関心は高くなく、国産Bセグメントしか買ったことがない人物だったが、そのドライブで一発で魅了されたのだという。驚きはしたが、刺さる気持ちは理解できる。そういう強烈な誘引力がこのクルマにはある。
もっとも、この500Cの余命もそう長くはない。先進安全システムの装備が義務化されたあかつきには日本での販売はできなくなるし、1.2リットル4気筒や0.9リットル2気筒がディスコンになれば現在は6速MTのみの1リットルハイブリッドにデュアロジック自動変速機版が追加されないかぎり、販売は終了してしまうだろう。フィアットはバッテリー式電気自動車『500e』を後継モデルに位置づけており、エンジン版の500シリーズは販売が許される限界まで現行モデルを継続生産し、フルモデルチェンジすることなしにディスコンにするのだろう。何とも言えないイニシエのテイストに浸りきれるのも、そろそろラストチャンスかもしれない。
◆見た目は似てるがまるで違う!キャンバストップとフルオープン
要素別に少し細かくみていこう。まずは500Cの圧倒的ハイライト、電動オープントップから。総論で述べたように、開閉は大きく2段階。屋根の上部だけを開けるキャンバストップと、そこからリアウインドウを畳んでさらに開口面積を拡大するフルオープン。操作はすべてひとつのスイッチで行い、キャンバストップが全開になるところで一旦停止、さらにもう一度スイッチの開放側を押すと全開になる。
キャンバストップモードの場合、フィールは一般的なキャンバストップそのもの。屋根からの採光は豊かになるが風の巻き込みはごく小さく、車内はクローズドと大して変わらない平穏な状態である。一方のフルオープンはというと、リアウインドウの部分まで畳んでも幌がかさばるので見た目的にはキャンバストップと大して変わらない印象なのだが、ところがどっこい、たったそれだけのことで500Cがまったく別モノのクルマになるのである。
両モードの開放感の違いは乗ると驚くほど。違う点はまず採光性で、フルオープンにしたときの室内の明るさは2倍以上と言いたくなるくらい。前席でも十分にそう感じられるが、それ以上に違うのは後席。頭の後方まで空がひらけるため、4座ロードスターに乗っているのと変わらないくらい爽快だ。
もう一点大きく違うのは車内の空気の流れ。キャンバストップの時は車内の空気はほぼ止まっているような感じだが、フルオープンにすると頭から顔にかけて風が撫でつけるようになる。さらにドアのウインドウを全開にすれば、全身に風を浴びるようなフィールだ。500Cはピラーやルーフの枠が残る、イタリアではカブリオ、あるいはトラスフォルマービレなどと呼ばれる形式だが、屋根と窓を全開にしたときの開放感はそれがないフルオープンとほとんど変わるところがなかった。
ということで筆者はツーリング中、写真撮影の時を除くとほとんどキャンバストップにせず、どんな猛暑でも基本はフルオープン、天候悪化時のみクローズで走った。幌が畳まれた時の上端がいささか高く、後方視界が悪くなることがオープントップ時の弱点として上げられるが、そんなものはちゃんと注意して見ればいいと考えた。そのくらいフルオープンは気分が良く、途中で飽きることもなかった。ちょっとしたお出かけ時にも、クルマに乗り込んだらまず屋根を開けるという作業から入ったほどである。
旅程の大半は真夏のバカっ晴れという絶好のドライブ日和。猛暑下でオープンで走るなどバカじゃなかろうかと思われるかもしれない。もちろん暑いことは言うまでもない。ゴー&ストップの多い街中では風が来ずに苦行になる。が、40km/hくらいで動いていれば風が汗をどんどん蒸散させてくれるので意外にも平気だった。熱中症予防のためこまめな水分、塩分の補給は当然必要だが、暑さで頭がぼうっとするようなことはまったくなかった。ただし、強烈な直射日光を浴びながら1日走れば別人種になったかと思うくらい真っ黒に日焼けするので、それが気になる場合はSPF50の日焼け止めクリームをこまめに塗り込む必要があろう。
◆85km/hまで開閉可能なトラスフォルマービレ方式の圧倒的アドバンテージ
総論で述べた最高気温39度は滋賀の琵琶湖畔、近江八幡において記録したもの。その暑さに耐えながら国道477号線、通常鈴鹿スカイラインを経由して尾張平野に向かった。最高標高地点が800m超というこのルートはなかなかいいワインディングロードで、武平峠に向けてどんどん高度を稼いでいく。すると、平地の猛暑が嘘のような涼やかな風が車内を吹き抜けるようになる。気温30度を切ると気分はもう天然冷房だ。
県境を越えて三重の平地に下りると気温は再び上がったが、ピーク時のような暑さはもう過ぎていた。海の近くでは潮の匂い、夜に山間部を駆けるときには森の匂い。沢が近づくと空気がひんやりとしてくるなど、空気は刻々と変化する。鎧のような屈強な車体によって外界と完全に隔絶された快適な室内で過ごすのとはまったく異なる、オープンならではの快楽である。
このオープントップの美点は高速走行時でも開閉可能ということ。フルオープンにしていると閉じるときにまずリアウインドウ部を展張、それからキャンバストップ部を閉めるという2段階のプロセスが必要になるが、トンネルが見えたと思ってから操作しても大抵はトンネルに入る前に閉じ切るくらいには動きが機敏である。トンネルが連続する区間を過ぎたらまた走りながら開けて元のフルオープンにすればいい。
この旅では往路は山陽、復路は山陰を経由した。どちらもトンネルが連続する区間があちこちにあるが、このシステムのおかげでオープンで走れる時間は圧倒的に長かった。通常のオープンカーも最近は幌式、バリオルーフ式とも走行時に開閉可能なものが増えているが、85km/hまで開閉可能というクルマは聞いたことがない。この点はトラスフォルマービレ方式の圧倒的なアドバンテージと言え、この自在感のためならピラーや屋根の枠が残ることくらい何でもないというのが筆者の印象だった。
◆乗り心地は古典的欧州車の味
2015年に5速MTモデル『500S』の900km試乗記でもお伝えしたことだが、500シリーズの乗り心地や操縦性は実に良い。単に可愛いというだけでは500は欧州Aセグメント市場を席巻し、あまつさえ他国ブランドはほとんどお呼びでないという閉鎖市場ドイツで存在感を示し続けることはできなかっただろう。
走りと乗り心地を支えているのは2003年に発売されたミニワゴンの第2世代パンダが初出のフィアットミニプラットフォーム。登場から今年で丸20年だが、ADASを組み込めていないなどアップデートは停滞しているもののシャシーの能力としては今もって一級品である。サスペンションは前マクファーソンストラット、後トーションビームというきわめて一般的な構成で、前後両アクスルにロールを抑制するスタビライザーを装備している。
走りのチューニングはやんちゃなイメージのルックスとは裏腹に徹底した安定性コンシャス。高速道路、一般的な郊外道だけでなく前述の鈴鹿スカイラインや九州の山岳地帯などワインディングロードも積極的に走ってみたが、そこで印象的だったのはリアサスが非常に柔らかいこと。タイトコーナーを回り込んだところでスロットルを開けるとリアサスが深くロールしてアンダーステアを抑制しながらコーナーを脱出する。
面白いのは動きはマイルドで終始安定しているのに、感覚的には非常にスピーディで刺激的なこと。185/55R15という1040kgのボディには十分すぎる能力を持つタイヤを履いているので絶対的な速力も十分にあるが、それ以上に速く感じられる。この特性はのんびり走っている時もどこかわくわくさせられるというテイストにも通じる。
こんなネアカなセッティングをよく作れたものだと感心させられたが、チューニングばかりではなく、2300mmと超ショートホイールベースであることも一役買っていた可能性もある。現代ではこれほどのショートホイールベース車は数少なく、ホイールベースが短いクルマって楽しいものなんだなと再認識した次第だった。
乗り心地はとてもいい。ビシッとダンピングの効いた現代的なライドフィールではなく、サスペンションストロークをゆるゆると積極的に使う古典的欧州車の味だ。ホイールの振幅は大きいが暴れるような動きはきっちり取り去られているので、どこを走っても極端に乗り心地が悪化することがない。平滑な舗装面の高速でもガタガタ道の九州山地でも常に足つきが良く、路面変化を舐めるようなテイストが維持された。
後編ではパワートレイン、居住性、ユーティリティなどについて述べる。