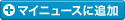スズキの軽ベーシックカー『アルト』で3600kmあまりツーリングする機会があったので、インプレッションをお届けする。
アルトの第1世代が登場したのは1979年。スターティングプライス47万円という低価格、さらに4ナンバーの商用車仕様で軽自動車税も安いという徹底的なバジェット志向の商品性でシティコミューター需要をごっそり掘り起こした。その後、5ナンバーの乗用モデル主体にシフトしながら庶民の足として発展したが、1993年にスズキがトールワゴン『ワゴンR』を登場させたのを機に軽乗用車の主流はトールワゴン、さらに全高1700mm以上のスーパーハイトワゴンに移り、アルトは次第に傍流ブランドになっていった。
2021年に登場した現行アルトは第9世代。アルトの源流であった4ナンバー商用車仕様はラインナップされず、初めて完全な乗用車専用モデルとなった。全高を第8世代から5cm高めて居住空間を拡大する一方、ターボエンジンを搭載するホットモデルを廃止して自然吸気のみとするなどグレード構成も大きく見直された。
パワートレインにはマイルドハイブリッドとそうでないものがあるが、非ハイブリッドも回生電力を蓄えるリチウムイオン電池パックを標準装備するなど低燃費志向が強い。価格は最上位グレード、FWD(前輪駆動)のオプション非装着車で125万9500円と、お洒落系モデルの『ラパン』のスタート価格とちょうどクロスオーバーする設定である。
ロードテスト車はその最上位グレード「HYBRID X」のFWD。アルトはダイハツ『ミライース』『ミラトコット』などと並ぶ超シンプルなモデルだが、HYBRID Xはシリーズ中唯一運転席シートリフターとチルトステアリングの両方を装備する。有償オプションはルーフ2トーンカラー塗装、ディスプレイオーディオ、フロアマット、ETC2.0車載器、ドライブレコーダーなど。
ドライブルートは東京〜鹿児島周遊で、総走行距離は3624.8km。往路は瀬戸内、復路は日本海ルートを走行。おおまかな道路種別は市街地2、制限速度70km/h以下の郊外路6、制限速度80km/h以上の郊外路および高速道路2。加えて短い山岳路といったところ。本州内は終始1名乗車、九州内では1〜4名乗車。エアコン常時AUTO。
レビューの前にアルトの長所、短所を5つずつ挙げてみる。
■長所
1. 市販車トップランナー級の燃費をシンプルな工夫で簡単に出せる。
2. 旧型から一変したヌルリと快適な乗り心地。
3. 前席、後席とも乗降性、居住性に優れる。
4. シンプルすぎて車内、車外とも清掃がメチャクチャ楽。
5. 軽いおかげで意外に速い。
■短所
1. 居住区にスペースを食われて荷室が狭い。
2. 室内の収納スペースが不足気味。
3. 後席の背もたれが分割可倒式でなく、2名or4名乗車の二者択一になる。
4. 各部のタッチはもちろん質素。
5. ADAS(運転支援システム)の類は用意されない。
◆本物の「アフォーダブル」を名乗る資格
オンライン発表会で鈴木俊宏・スズキ社長が開発意図を「下駄を極める」という言葉で表現した第9世代アルト。実際にドライブしてみた印象を一言で表現すると「これぞ本物のアフォーダブル(お手頃)」。
現代においてこれ以下は新車の顧客ではないという最低価格帯の商品だが、そのバリューの高さはテストドライブ前の予想をはるかに超えるものがあった。コストを限界まで絞りながらも設計は実に良心的で、乗り降りしやすく、車内は明るく開放的。乗り心地は大変気持ちよいもので、車内は思いのほか静か。近距離用途のクルマでありながら疲労感は小さく、長距離移動もバッチリだ。そして燃費は飛びきりに優れる。
アフォーダブルという言葉に明確な定義がないため、最近ではコストパフォーマンスが高いことをアフォーダブルと安易に言い換えるケースが多々見受けられる。これは自動車業界に限った話ではなく、アパレルの世界ではアフォーダブル・ラグジュアリーなどというわけのわからない用語まで生み出される始末だ。
が、アフォーダブルを名乗るにはやはり価格の安さが絶対条件となると思う。高価なストロングハイブリッドカーやBEV(バッテリー式電気自動車)に手が出ないという人を含め、誰もがこのクルマに乗ることによって低CO2、省資源を実践することができ、誰もが気持ちの良い移動を楽しむことができる。こういうモデルこそアフォーダブルを名乗る資格があるというものだろう。
アルトのある暮らしは東京〜鹿児島の往復を含めて2週間ほどだったが、このバジェット価格でこれだけの利便性を提供してくれるのに何の不満があろうかという気分だった。ロングランにおいては「頑張ってくれてありがとう」とクルマに言いたくなるような乗り心地の良さが有り難く感じられたし、鹿児島エリアでは乗降性の良さやキャビンの開放感の高さがモノを言って、市街地走行から3〜4名乗車でのプチ遠乗りまで、何でも楽しくこなすことができた。もちろん高価なクルマが持つようなハイテク機能はほとんどないし、性能も燃費以外は劣る。そこをユーザーがカバーするのもまたアルトの楽しみのひとつに思えた。
日本の貧困化、衰退化といった話をよく耳にするが、そうは言ってもまだまだ豊かであるため、アルトのようなバジェットカーは価格が安いにもかかわらず傍流に甘んじている。が、クルマの価格がどんどん高騰していることを考えると、こういうクルマの有難味がふたたびクローズアップされる時代が来る可能性は十分にある。
クルマの価格が上がることへの対応策としてやたらと喧伝されているもののひとつにカーシェアがあるが、家の近くに拠点があるとは限らない、使いたいときに必ず空きがある保証がないなど、カーシェアは決して万能ではない。クルマで24時間、自分が望む時に望むところへ行ける、移動の自由を担保する道具としてみるならば、1台を占有できる自己所有のほうが断然いいに決まっている。クルマがないこととアルトがあることの違いは、アルトがあることとロールスロイスがあることの差より1兆倍大きいというのが筆者個人の考え。先行き不透明なこのご時世、アルトのようなクルマがいついつまでも存在し続けてほしいものだと心底思った次第だった。
◆乗り心地に全振りした、軽ベーシックの新境地
要素別に詳しくみていこう。まずは走りや乗り心地を決定づけるシャシーから。プラットフォームは大幅軽量化を果たした第8世代のキャリーオーバーだが、シャシーチューニングのポリシーは180度転換と言ってもいいほどに変わった。
旧型はノーマル系のグレードでもサスペンションのロール剛性が高く、ワインディングロードではステアリングを切ると超軽量車体が横っ飛びするかのように反応する痛快さがあった。第9世代はそれとは真逆でサスペンションは超ソフト。車重は依然として軽いがハンドリングはダルで、操縦性を積極的に楽しめるような要素は雲散霧消したが、そのかわりに第8世代の弱点であった乗り心地は劇的に改善。綺麗な道から荒れた道までぬるりとした気持ちの良い乗り心地と良好な直進感が維持されるようになった。
どちらを好ましく思うかは人によるだろうが、筆者は乗り心地に全振りした第9世代こそ軽ベーシックの新境地であるように思った。たしかに第8世代は楽しかったが、レスポンシブなハンドリングは瞬間芸のようなもの。車重700kg強という軽量ボディでここまでゆるりとした乗り心地を実現したことはそれ自体が感動ポイントだった。
柔らかいサスペンションと一口に言ってもテイストはさまざま。第9世代アルトのそれは、言うなれば弱いダンピングが着実に効いているという乗り味である。たとえば荒れた国道などで深めのアンジュレーション(路面のうねり)を踏んだり片輪が轍を踏んだりしたとしよう。サスペンションが柔らかいため車体の揺動は大きめに出る。普通ならそれがボヨンボヨンとした動きにつながったりするのだが、アルトは車体の軽さが寄与しているのか、ショックアブゾーバーの減衰力が高いわけでもないのにその収まりが早い。無理に揺れを止めようとしているわけではないので揺れのスピードも遅い。結果、体へのGのかかりが穏やかで、大変ナチュラルに感じられた。
揺れ幅は大きいが揺れのスピードは遅いというこの乗り味は自動車工学が今ほど進化していなかった1980年代の欧州小型車、それもスポーツタイプでない一般グレードのクルマに似ている。過去の運転経験に照らして乗り味が似ていた例を挙げると、筆者が初めて海外旅行に行った時にレンタカーで乗ったシトロエン『AX』、第2世代フォルクスワーゲン『ポロ』など。50代以上の人にとっては一種のノスタルジーを覚える乗り味かもしれない。自動車工学が成熟の域に達しつつある今日の技術を用い、コストの限界を突き詰めながら丁寧にセッティングを行うとこういうテイストになるのかと、興味深く思われたりもした。
◆柔らかいサスと軽量ボディが活きる、中速域のクルーズ
そんな第9世代がとりわけ得意としていたのは中速域のクルーズ。ちょうど地方で町と町の間を流れの良い地方道やバイパスを通って移動するようなシーンである。舗装の老朽化で路面がかなり荒れているような箇所での振動吸収はなかなかのもので、引っかかり感の少ないサスペンションの動きは本当に好感が持てた。アルトはサスペンションストロークが小さいので、バンピングが大きくなるとその上下動幅を使い切り気味になるのだが、底付きの衝撃を吸収するバンプストップラバーの硬度が適切なのか、ドシンと衝撃を食らうような感じではなかった。このへんの作り込みも大変上手いと思わせるものがあった。
柔らかいサスペンションの副次的効果としては、ボディシェルにかかるストレスが小さいということがあった。サスペンションのバネ定数が高いとコーナリングGや前後左右の揺れが車体側に急激にかかるのでボディをそれに耐えられるよう強化しないと乗り味が悪くなる。アルトはベーシックカーであるにもかかわらず超ハイテンシル鋼板を多用するなどかなり頑張った作りになっているが、それでも超軽量を保ったままの高剛性化には限界がある。サスペンションがやわやわでGのかかりが穏やかなアルトは、ボディ強度に過度に依存することなくガタつき、ビリつきを抑制することに成功していた。
柔らかいサスペンションのネガティブな部分は操縦安定性に集中していた。減衰力が低いながらも揺動をしっかり止めていたショックアブゾーバーも、コーナリングの荷重の変化のような大きな力になると止める力の弱さがモロに出てくる。コーナリング姿勢の安定性は正直低く、軽量車体であるにもかかわらず山岳路を小気味よく走れるという感覚はなかった。そこはクルーズフィールの良さとトレードオフになったと前向きに考えて、山道はのんびり走るが吉であろう。なお、タイヤは155/65R14サイズと車重に対して十分な能力があるので、絶対性能に過度の不安を抱く必要はない。
バイパスより速い高速道路の場合、クルーズフィールは速度レンジ次第となる。新東名120km/h区間を一番速い流れに乗って走らせてみたときはさすがに少々クルマに無理をさせているという感があったが、新東名に比べて空力特性の影響が小さくなる山陽道や九州道の100km/h区間になると結構良好。アンジュレーション通過時に少々大きくバウンシングしても針路の乱れが小さく、バイパスクルーズと同様に直進性の良さが運転を楽なものにした。もっとも快適性は80km/h前後まで落としたほうが断然高く、のんびり走れる山陰道や南九州道のような道路への適合性が最も高いように思えた。
タウンライドは速度が低く、クルマの性能差が出にくいのだが、ハーシュネス(突き上げ感、ザラザラ感)カットがそこそこ上手くできているため、鹿児島市電の軌条などきつめの段差を乗り越える時も大きなストレスを感じずにすむだけの快適性は確保されていた。
もう一点、市街地で良かったのは小回り性能。最小回転半径は旧型より20cmプラスの4.4mと少々悪化したが、ライバル比較では依然としてトップランナー級である。アルトはボンネットの左右にヘッドランプに続くよう尾根が盛り上がっているようなデザインを持っているためボンネット先端の位置をことのほか把握しやすく、その小回り性をリアルフィールドで目いっぱい使えるというのも美点だった。
◆先進装備、テレマティクスは弱点か
アルトはADAS(先進運転支援システム)をオプションでも装着することができず、この点は最も弱いところのひとつ。前車追従クルーズコントロールやステアリング介入型の車線維持アシストがないため、ロングツーリング中も加減速、ステアリング保持を100%ドライバーが自力でやる必要がある。
筆者はそんなものが存在しなかった時代が長かった世代なので、それなら100%自力で運転すればいいだろうという程度にしか思わないが、ADASがあるのが半ば当たり前という若年層には不安材料となるかもしれない。なお衝突軽減ブレーキはステレオカメラタイプのものが装備されている。夜間に歩行者を検出可能だが、自転車には未対応。事故時の緊急通報システムは装備されていない。
テレマティクスについては今日流行りのコネクティビティモジュールは非搭載。ロードテスト車はカーナビも未装備で、代わりにApple CarPlay、AndroidAutoに対応したディスプレイオーディオが装備されていた。筆者は実はディスプレイオーディオで十分と考えるクチで、価格を抑えるという観点でこの仕様にむしろ好感を抱いた。
GoogleMapはルートガイダンスの精度がカーナビ専用機に劣るという声が多く、事実その通りだと思う。が、日本でもヨーロッパでもアメリカでも紙の地図を頼りにドライブする時代が長かった身としては、地図上のどこに自分がいるかがGPSでわかるというだけで上等すぎる。ガイダンスが間違っていたとしても、リアルワールドの状況に合わせてそこだけ自分の判断で運転すれば何の問題もない。カーナビ専用機も一応用意されているので、完全なフールプルーフでなければイヤだというユーザーはそれを装備すればいいだろう。
後編ではパワートレイン、居住性、ユーティリティなどについて触れようと思う。