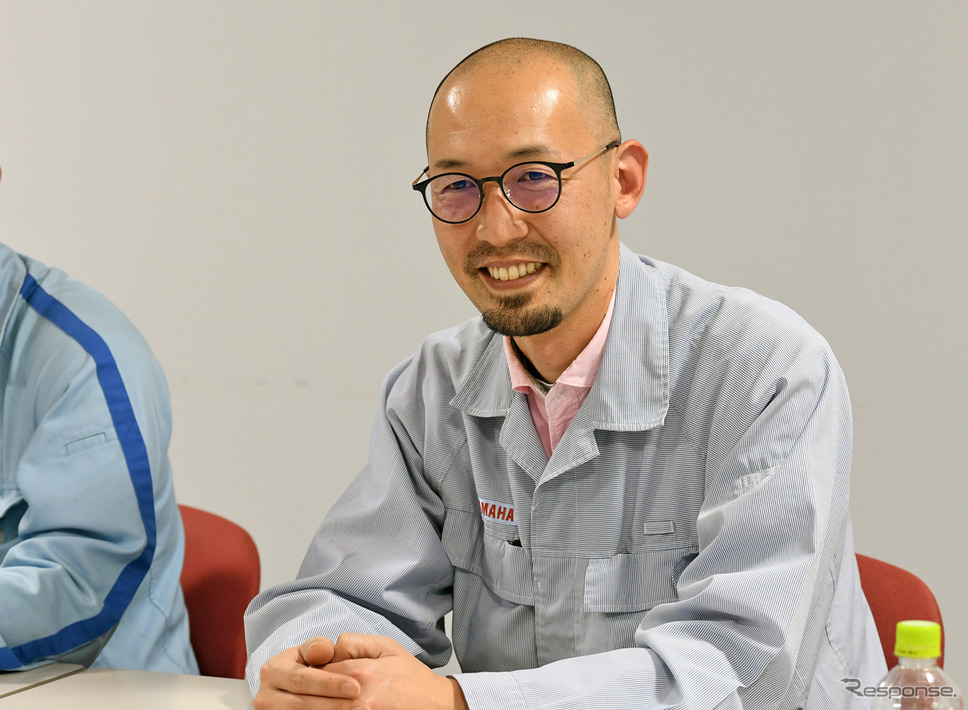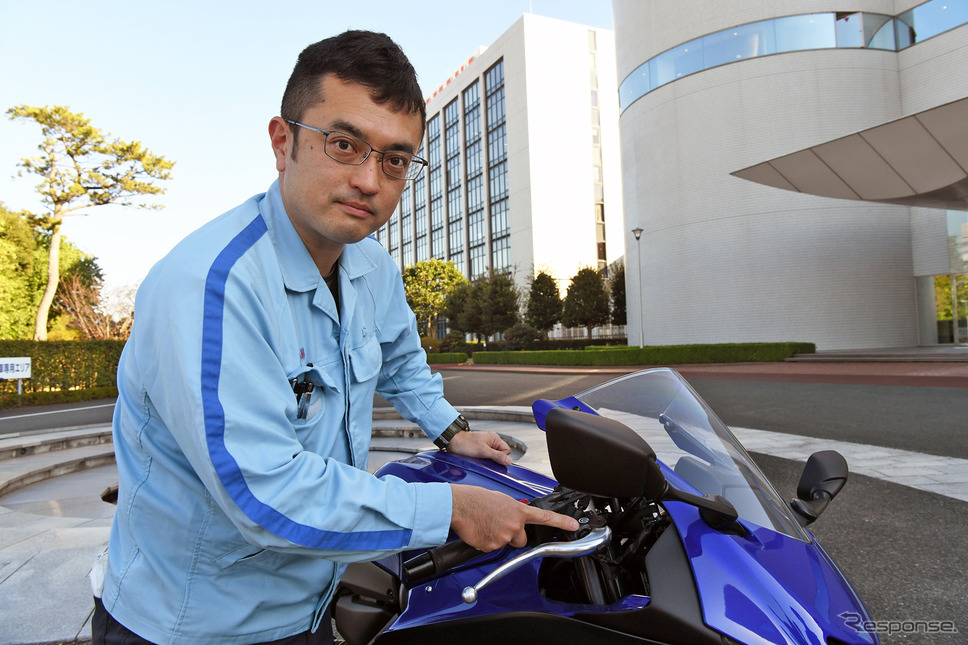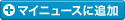2021年5月、ヤマハ発動機は新型ミドルスーパースポーツ『YZF-R7』(689cc/並列2気筒)を発表し、欧米でのリリースを開始している。日本でも2021年冬以降の発売が予定されており、今回それに先駆けて開発メンバーに様々な話を聞くことができた。
インタビュー第1回目は、プロジェクトリーダーを中心に、開発プロジェクト立ち上げの経緯やコンセプトを聞く。
【インタビュー参加メンバー】
今村充利
PF車両ユニット PF車両開発統括部 SV開発部 SP設計グループ プロジェクトリーダー主査
車体設計や外装設計に携わり、ビッグスクーターからスーパースポーツ、モペットと幅広く担当。YZF-R7では開発プロジェクトリーダーを務めた。現在の愛車はXSR700。
蓮見洋祐
PF車両ユニット PF車両開発統括部 車両実験部 プロジェクトグループ主事
車両実験のプロジェクトチーフとして進捗状況の管理の他、実走も担当。これまではYZF-R25/R3やボルトなどを担当してきた。愛車はセロー、TRX850、R1-Zなど。
初代「MT-07」開発時から描かれていたロードマップ
----:YZF-R7は、2021年に登場した現行の『MT-07』から派生していますが、そのアイデアはいつ頃からあったものなのでしょうか?
今村:アイデアという意味では、初代MT-07(2014年)の開発時からすでに思い描かれていたようです。私自身はまだ携わっていませんでしたが、スポーツツアラーの『トレーサー700』やスポーツヘリテージの『XSR700』へ発展するロードマップはすでに存在していましたし、その延長線でスーパースポーツの可能性が模索されたのは自然な流れだと思います。そのため、いざ現実になった時に無理なく対応できるよう、MT-07には最初からそのエッセンスが込められていたと聞いています。
----:実際に開発が始まったのはいつ頃のことでしょうか? また、初代と2代目(2018年)の時は見送られ、そのベースに現行のMT-07が選ばれた理由をお聞かせください。
今村:開発が始まったのは、2017年のことです。大きなきっかけは、北米市場における動向の変化ですね。というのも、その少し前からミドルクラスの2気筒モデルをカスタムして、サーキット走行を楽しむユーザーが増え始めていました。カスタムといってもそれほど大げさなものではなく、フロントフォークを倒立タイプに換装したり、ハンドル位置を下げたり、カウルを装着するといった内容で、そうしたキットパーツを作るメーカーやショップが徐々に増加してきました。
ローカルレースも開催されるようになり、現地スタッフからもポジティブな声が届くようになりました。そのタイミングと現行MT-07の開発が重なり、YZF-R7の構想が具体的に進められることになった、というのが大まかな経緯です。
----:なるほど。アフターパーツメーカーとユーザーとメーカーが三位一体になってトレンドを作るという意味で、理想的な展開に感じられます。ミドルクラスの、あるいは2気筒エンジンの需要は世界的にも高まっているのでしょうか?
蓮見:700cc前後の排気量を持つ2気筒エンジンというのは、なにかとバランスのいいユニットです。持て余すほどパワフルではなく、それでいてトルクはしっかりあり、サーキットの大小を問わず誰が乗っても楽しめるところが、広く支持されている要因だと思います。レース用に仕立てたとしてもそれほどのシビアさはなく、エントラントの皆さんがどんぐりの背比べ的にスピードを競い合えるところが人気の秘密でしょう。北米だけでなく、イギリスのマン島TTや日本の岡山国際サーキットでもこのクラスのツインレースが始まっていますから、さらなる盛り上がりを期待しています。
ちょうどいいモデルがない「空地」状態だった
----:そうしたツインレースにおけるライバルは、どういったモデルですか?
今村:やはり、スズキ『SV650』やカワサキ『Ninja650』などですね。ただ、SV650はあくまでもネイキッドで、Ninja650はどちらかと言えばツアラーの要素が強い。つまり、純然たるスーパースポーツが存在しなかったわけです。セパレートハンドルやフルカウルのスタイルに憧れがあったとしても誰もがカスタムするわけではなく、弊社のモデルで言えば『YZF-R6』の中古車がそうしたユーザーの受け皿になっていることが分かりました。
----:新車ではなく、中古車なのはなぜでしょう?
今村:最大のネックは価格でしょう。YZF-R6はレーシングマシン然としたポテンシャルを備えているため、そこはご容赦頂きたいのですが、だからと言って『YZF-R25』や『R3』では物足りないというユーザーがいらっしゃるのも事実。そういう方々の選択肢が中古のYZF-R6だったというわけです。もっとも、そのエンジンは超高回転型の4気筒ですからハイスペック過ぎるという問題もあり、ちょうどいい排気量帯にちょうどいいパフォーマンスのモデルがない、言わば「空地」状態だったのです。そのニーズに応えられる新型モデルを、リーズナブルな価格で投入することが、我々の大きな使命のひとつでした。
----:よく分かりました。時ほとんど同じくして、イタリアのアプリリアから『RS660』(659cc/並列2気筒)が登場したのも、おそらくそういう市場背景に後押しされたものだと思います。
「R7」という車名への葛藤と決意
----:ところで、「YZF-R7」という車名に関して伺いたいのですが……。
今村:おっしゃりたいことは分かります。これに関しては社内でも喧々諤々がありましたから。
----:やはりそうですか。1999年に登場したオリジナルのYZF-R7(型式名OW-02)は、当時のスーパーバイクレースに参戦するために開発された、いわゆるホモロゲーションモデルです。生産台数がわずか500台だったことに加え、日本円にして約400万円という価格も話題になったプレミアムモデルゆえ、車名復活に対しては慎重な意見があったことと推察します。
今村:なにせ、あのYZF-R7ですからね。市販車最高峰レースでのタイトル獲得を目的にしたマシンの名を、まったく出自が異なるモデルに付けてもいいのか、という問題は確かにありました。たとえば、「YZF-R07」を名乗るという案もあったのですが、それだとYZF-R25/3/6/1という一連の流れから外れた亜流のようなイメージがありますし、MT-07との差別化も中途半端なものになりかねません。
新型YZF-R7には「Fun Master of Super Sport」というコンセプトを掲げ、それにふさわしい仕上がりだと我々は自負していますから、かつてのYZF-R7と立ち位置が違っていたとしても、新しい時代のスーパースポーツとして受け入れて頂ける。我々はそう考え、自信を持ってその名を与えることにしました。
----:なるほど。MT-07に備わっている軽やかなハンドリングや、スロットルをどんどん開けていける過渡特性はすでに体感していますから、YZF-R7には「Fun」の要素、つまり「楽しさ」がさらに凝縮されているものと想像します。次回はその実現のために、どのように開発を進めていったのかを詳しくお聞かせください。
(第2回へ続く)