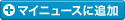ゼネラルモーターズ・ジャパンは5月19日に開催されたシボレーファンデイ2023において、コルベット生誕70周年を記念し、待望のシボレー『コルベットZ06』を日本初公開した。そこでこのクルマの商品特徴などについて、担当者に話を聞いた。
◆C8がリアミッド、右ハンドルを採用したわけ
---:まずはZ06の前に現行C8の特徴から教えてください。
ゼネラルモーターズ・ジャパンプロダクト&パブリックポリシーディレクターの上原慶昭さん(以下敬称略):コルベットは今年70周で、現行は8世代目、C8です。この一番の特徴は、エンジンがミッドシップレイアウトになったことで、これが最大の変化点ですね。それとゼネラルモーターズ・ジャパンとしては、コルベット史上初の右ハンドルが作られたことで、日本仕様は全て右ハンドルです。
ではミッドシップレイアウトになぜなったのか。7世代目まではフロントエンジン、リア駆動というレイアウトで、アメリカンマッスルの象徴的なスポーツカーという位置づけでした。一方、コルベットの開発陣は5世代目、C5の時からコルベットレーシングとしてレース活動をサポートしており、サーキットで様々な勝つ手立てを取っいくのですが、そのうちのひとつは当然ながらエンジンパワーを上げることがあります。これは割とやりやすいんですね。例えば過給をする、大きなスーパーチャージをつけるということをやって来ました。そうした中でどうしてもタイムを刻み切れなかったのは、リアのトラクションをどれだけ確保するかだったのです。
つまり、極端ですがパワーはいくらでも増やせますが、リアがグリップしない。コーナーの立ち上がりでどうしてもロスが出て、“あの人に勝てない”ということが出てくるわけです。そこで開発チームとしては、かなり前からリアにもっと荷重を置きたいということを目標にしてきました。ただ、ゴロッと(レイアウトを)変えると投資もかかるものですから、それがこのC8のタイミングになったのです。
これまではフロントエンジンのリア駆動で、ハンドリングのために重量配分も50:50を目指してやってきましたが、それでも後ろの荷重が足りない。そこでC8は、基本的に40:60の荷重にしました。重たいエンジンを真ん中にレイアウトして、なおかつホイールベースを縮めているんです。その結果として非常にコンパクトに旋回できるようになるとともに、重量配分を後ろに置いて、コーナーの立ち上がりの時にグッと踏ん張るようにした。それがこのC8のトピックです。
次になぜC8で右ハンドルできたかです。ストレートに申し上げてC7ではできなかったんです。大きなV型8気筒をフロントに搭載していましたから、ステアリングシャフトが反対側につけられないんです。レイアウト上、とても無理。だからできなかったんです。しかし今度はエンジンをリア側に搭載しましたから、フロントはかなり自由度があるのでやろうと決めました。しかし、開発した人間はそれでも大変だったとものすごくいわれる。もっともっと簡単にできるかと思ったけれど、とても苦労したといわれますね(笑)。
---:ではC8の命題はトラクションだったわけですね。
上原:まさにその通りです。いかにコーナーを早く立ち上がるか、そこでのロスをなくすかということです。
ゼネラルモーターズ・ジャパンププロダクト&パブリックポリシープロダクトマネージャーの中野哲さん(以下敬称略):リアのトラクションを100%路面に伝えるためにはやはりミッドなんですね。50:50に対して40:60になりリア荷重が10%増えたことによって、トラクションがうまく生きました。限界での横Gについても1.22Gという非常に高い数値を達成していますので、やはりミッドじゃないと極められないところまで来てしまっていたのでしょう。
上原:先代でエンジンパワーを上げたものをレーシングトラックで走らせると、その前のモデルよりもタイムが伸びないんです。つまりトラクションなんです。それを何とかするためにタイヤをかなりエグゾチックな柔らかいタイヤにして、とにかく(路面に)食いつかせようとしていたのですが、本当はもっと自然にリアにトラクションをかけたかったのですね。
そうした結果としてC8はすごく運転しやすいんです。限界を越えたらどこかに飛んでいくんじゃないかという心配が全くない非常に扱いやすいクルマに仕上がっています。
中野:安定した走りという面では、C8になってサスペンション形式を変えたこともあります。リーフスプリングをやめてコイルスプリングになりました。リーフは軽量化ということで採用していましたが、一方でクルマが跳ねたりして接地性に問題がありました。それをコイルに変えたことによってかなり向上しましたし、ブレーキもこのパワーを受け止めるためにモノブロックにしました。
◆ストリートリーガルレーシングカー
---:そして今回お披露目されたZ06についてです。こちらの特徴はいかがでしょう。
上原:歴史的に振り返ると初代のコルベットからレーシングシーンに耐えられるような高性能パッケージがありましたが、やはり5世代目から特別な高性能モデルをラインナップしています。8世代目を開発にあたっては既にこのクルマでのレース活動は決まっていました。つまりレーシングカーも仕上げなければいけないわけです。同時に高性能のZ06も開発することが決まっていましたので、通常のミッドシップ化したC8を開発する傍らで、レーシングカーとZ06も一緒に開発していきました。一足先にレーシングカーの「C8.R」がレースに出ていますけれども、つまりそれがZ06のベースになっているという言い方も出来ますね。
では、C8に対してZ06がやりたかったこと。それは、GMの開発陣の言い方でいうと、“ストリートリーガルレーシングカー”、発想としてはそうなんです。ですからZ06は、C8.Rというレーシングカーを公道でも乗っていただけますという位置付けですね。では、C8に対してC8.Rは何を目指しているのか。これはもっとリアにトラクションが欲しいことと同時に、よりエンジンを強固にし、レースシーンで勝てるようにより高回転型の性能にしたいということでした。そこでエンジンを新設計しているのです。C8は6.2リットルV型8気筒のOHVで、伝統的な味が好評です。それに対しZ06とZ8.RはV型8気筒5.5リットルDOHCです。なおかつフラットプレーンを採用し、まさにレーシングエンジンのような高回転型のエンジンを最初から狙って作っています。それをC8.Rに先行して搭載し耐久レースなどに出ており、そのエンジンがZ06にも搭載されているのです。
レッドゾーンの始まる8600rpmまで回すとどんどんパワーが出てきます。そしてさらにトラクションを高めるために、シャシーも前後とも幅広くしていますし、装着しているタイヤも、径を上げて、なおかつ幅広くしている。とにかくそこでトラクションを確保するということもさらにやっているのが特徴です。
中野:それから、C8.Rからその技術をZ06に生かすところですが、レーシングカーに使っていたテストアプリケーションを全部使って、このデザインに生かしているんです。単に格好だけではなくて、機能がデザインに生きている。今回も特にハイパワーになったエンジンの駆動力を路面に伝えるために揚力の調整、ダウンフォースですね。そこはものすごくこだわっていて、ノーマルのスポイラーは目立たないですけど、実はこれ、約300km/hで164kgもダウンフォースを得られるんです。C7より全然上がってるんですけれど、やはりダウンフォースがないと、結局パワーがあってもトラクションがかからずに逃げてしまう。ですから、このスタイルは格好だけではないのです。
◆排気音は日本では車検に通らない
---:さて、Z06の日本仕様とアメリカ本国仕様とで違いはありますか。
上原:まず排気系統が違います。アメリカ仕様はセンタークォート(中央の4本出し)で、先代までは全部そうでしたし、それも象徴的でしたね。現行Z06もアメリカでは同じなのですが、その真ん中は直管なんです。なので絶対に音で車検が通らない。そこで日本での車検に通る仕様に変えてもらいました。
それから現在C8はZ51という高性能パッケージを装備しています。その場合、クーリングシステムはフロント両脇に1基ずつとリアのサイドに3つ目のラジエーターが搭載されます。しかしZ06はもっと熱を出すのでもっと冷やさないといけない。そこでフロントの中央にもラジエーターを装備してフロントは計3つ。そしてサイドのエアインテークをさらに大きくして、左右両方にラジエーターを入れていますので、5つのラジエーターで冷却しています。
中野:また、両サイドのインテークはブレーキの冷却にも使われています。
---:メカ的な部分に関しては、マフラー以外の例えばエンジンの性能などは一緒ですか。
上原:一緒ですが排気が違うのでちょっとチューニングが違っています。馬力の値も排気が違うので本国仕様は670psに対し、日本仕様は646psです。
---:他に日本側からの要望としてはどんなものがあったんでしょう。
中野:結構細かいところなんですけれど、電動可倒式ミラーです。これは最後の最後まで揉めて、最後には落とされる寸前まで行きました。ただ、日本では絶対に欲しいと。なぜかというとアメリカと駐車方法が違うんです。向こうは頭から突っ込むのですが、日本はバックで入れて、乗員はドアミラーをすり抜けて出るんですよね。だから可倒式は絶対必要だといって、それを説明してビデオまで送って、こういうやり方で出るんだといって納得してもらいました。
---:今回の日本仕様は、外装はブラックで内装はアドレナリンレッドという仕様です。装備も上級としたワンパッケージですが、この仕様になったのははなぜでしょう。
中野:日本のお客様は一番良いものをお求めになるのですね。ですから一番良い上質なもので、“3LZ”を選んでいます。かつ今回ワンパッケージにしたのは、どうしても生産量に限りがあり、かつ本国でもバックオーダーがかなりあるのです。そこで最初はパッケージも台数も絞っています。従ってお客様が一番良いと思う仕様で、一番コルベットらしい走りを彷彿させるようなコンビネーション、黒のボディ、赤のシート、黒のホイールに赤のキャリパーという走りを予感させる、走りたいという意欲を掻き立てるようなコンビネーションで出したのです。
上原:因みにこのコンビネーションはアメリカの工場で作られている中で一番人気のもので。C8の一番人気のエクステリアカラーは赤なんです。赤、黒、白という順番。しかしZ06はダントツ黒なんですよね。世の中の人はみんなZ06は黒だと。そういう期待があるみたいなので、我々もその一番人気のものを出しています。
◆幅広くなったユーザー層
---:コルベット全体のお話に戻りますが、日本市場のユーザーは7世代目と8世代目で変わっていますか。
上原:興味を持ってくださるお客様の層がガラッと変わりました。7世代目までは左ハンドルしかありませんでしたので、コルベットといえばフロントエンジン、リア駆動の大排気量の左ハンドルというのが伝統で、それを好きな方が買ってくださっていた。しかしそれは一般的な目から見ると(当然ながら)かなり狭い世界感なんです。
中には、左ハンドルじゃないコルベットなんてコルベットじゃないと随分いわれましたけれども、そういう方もいまC8に乗っていただいています。それにしてもお客様の層はずいぶん幅広く変わりました。
中野:いままではやはり左ハンドルしかないので敬遠していた人がいらっしゃったんです。左ハンドルに乗っている人は右にも乗れるんですけど、右に乗っている人は、左には躊躇する傾向が強いですね。ですから新しい層が来たということは、右を出したことが大きいです。
また、価格帯も近かったことから、国産上級ミッドシップスポーツカー辺りに乗っていた方達にも興味を持っていただけました。検討しやすかったようです。
上原:デビューしたタイミングはほかにも国産スポーツカーが出てきましたが、コルベットは納期に時間がかかりましたので、その国産スポーツカーを購入したけれども、やはりコルベットに乗りたいと改めて選んでくださるお客様もいらっしゃいました。おそらくそういった方達は、左ハンドルしかなかった時には、踏ん切りがつかかったと思いますね。
実は今日、この会場を見ていて私個人としてベストステッカー賞と称したクルマがありました。それは若葉マークを付けたC8です。年配の紳士が一緒に乗られていて、その方はフェラーリもお持ちなのだそうです。このC8はその方のお嬢さんが最初のクルマとして乗るそうで、このようにこれまでとは全く違う層にも購入していただけています。