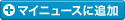F1ドライバーの角田裕毅が7日、オンラインの「ニューイヤー会見」に臨み、ルーキーシーズンだった昨季(2021年)の振り返りや、自身2年目となる2022年シーズンへの意欲などを語った。
◆F1新人年は「学びのシーズンだった」
2021年、日本勢7年ぶりのレースドライバーとしてF1初シーズンを戦った角田裕毅(つのだ ゆうき)は、2000年5月生まれの現在21歳。ルーキーシーズンはアルファタウリ・ホンダで全22戦(マシントラブルで決勝不出走だった1戦を含む)を戦い、10位以内入賞(ポイント獲得)が7回、最高位は最終戦アブダビGPでの4位だった。シーズン終盤には予選トップ10(Q3進出)の常連になる速さも見せている。
角田はまず、自身のルーキーシーズンを「ひとことで言えば、学びのシーズンだったと思います」と総括した。「いいこともありましたけど、苦戦することが多かったなかで、葛藤しながら、学ぶことが多かったです」。
2021年のF1はバーレーンでのプレシーズンテストから開幕戦バーレーンGPへ、という始まり方をした。角田は「テストから感触もペースも良くて、開幕戦のバーレーンGPでは(9位で)ポイントを獲ることができました」と好発進したわけだが、それが「F1を少し甘く見るようになったというか、(あとから思えば)自信を持ち過ぎてしまいました」との状況につながったと述懐する。
自信満々になってしまったことが遠因にもなり、「2戦目では大きなミス(予選Q1でクラッシュ)をしてしまいました。そこから流れが崩れ始めて、クラッシュも重なったりして、自信がどんどん失われていきました。負のスパイラルに陥ってしまいましたね」。
やがてチームから、「クラッシュをしないように」との指令を角田は受ける。クラッシュで走行時間が失われることが角田の将来に向けて良くない、というチームの判断は当然至極だった。実際に角田は「少しペースダウン」して、クラッシュしないことを最優先に走った。その結果、ミスは減った。だが、当然のことながらペース的には目立たないレースが続くことになる。
◆F1のレースウイークの過ごし方に大きな進歩
「何かを変えなければ」と角田自身が思っていたところで、ハード面とソフト面で変化が生まれる。
ハード面では、「シャシー(モノコック)をチェンジしたことでした」。10月の第16戦トルコGPでのことであったという。それ以前は「攻めていったときにリヤの挙動がナーバスになりやすかった」ことに悩んでいたが、シャシーを変えてからは「挙動の乱れはあっても、コントロールしやすくなって、自分がマシンを操っている感覚が戻ってきました」。
さらにソフト面で、新たな“コーチ役”がついたことも大きかったようだ。
アルファタウリはレッドブル陣営のセカンドチームという性格をもつが、2019〜20年にトロロッソ(現アルファタウリ)やレッドブルのレースドライバーとして走っていたアレクサンダー・アルボン、21年はF1のレースシートに就いていなかった彼が角田のコーチ役を務めることになったのだ(アルボンは22年、ウイリアムズでレースドライバーに復帰)。
そしてなにより、角田自身の「F1のレースウイークに対する考え方が変わっていった」ことが奏功したといえよう。
チームメイトであり、シーズンを通じて素晴らしい活躍を演じていた先輩ピエール・ガスリーのチームとのコミュニケーションの取り方から多くを学び、さらにはチャンピオン経験者のフェルナンド・アロンソ(アルピーヌ)が誰よりも遅くまで残ってチームとディスカッションしているという話にも感化されるなどしつつ、角田はF1のレースウイークをチームとともにうまく戦う術を身につけていったようである。
これら諸要素の相乗効果によって、シーズン終盤には負のスパイラルから抜け出しつつ、「結果も少しずつ良くなっていきました」。それにつれて、自信も蘇っていった。
◆ホンダへの感謝も胸に、最終戦で自己最高4位
「ハイライトは(第19戦)ブラジルGPだったと思います」。ブラジルGP(サンパウロGP)自体は予選Q3進出を逃すなど、これといった成績を残せたレースではなかったが、角田は「それまで感じていた負のスパイラルが消えていった感じがした」との旨を語り、シーズン最終盤の好走につながったことを強調している。
成績面での集大成は、間違いなく最終戦(第22戦)アブダビGPでの自己最高4位だった。
「ホンダ最終年(の最終戦)ということで、自分としても結果を残したかったですし、ホンダさんへの感謝を胸に走りました。4位で終えることができて本当に良かったですし、自分の自信という意味でも、開幕戦の頃に持っていた自信をさらに超えることができました。今年に向けてもいい感触で終えられた最終戦だったと思います」
「アップダウンもあって、かなりきついシーズンでしたが、いろんなシチュエーションを経験できてよかったと考えています」。学びのシーズン、その収穫はとても大きかったようだ。
◆大物感が漂う言葉の数々、高まる期待感
今季2022年もアルファタウリからのF1参戦継続が決まっている角田。まだF1で1年を過ごしたばかりの彼だが、会見冒頭で「F1ドライバーの角田裕毅です」と挨拶した姿からは、いい意味でなかなかの“太さ”が感じられた(風格や貫禄と呼ぶにはまだ早いと思うが)。
2021年シーズンは、走行中の無線での言葉の“暴れぶり”も国内外で話題になった角田だが、それについては「チームのムードをわるくするような言葉は良くない。反省しています」としつつ、「(話題になった当時は)賛否両論ありましたけど、正直、あまり気にはしていませんでした」と振り返る。
また、シーズン中に英国からチーム本拠があるイタリアに引っ越しているが、「英国にいた頃は(今にして思えば)結構だらしない生活でした」と、苦笑しながら反省できる。開幕戦終了時点で「F1を少し甘く見てしまった」という述懐も、これまでの日本勢にはなかった表現の仕方のように思えるところ。
太さ、とは、素直さ、なのかもしれないが、その言葉には大物感が漂っている。そして負けん気の強さや頑固さを自認しつつも、経験を重ねるなかで“場”に適応していく能力も角田にはありそうだ。
チームメイトのF1優勝経験者、2021年も入賞15回で最高3位という抜群の成績だったガスリーについても、「自分にとって素晴らしいお手本」として、敬意、感謝、親しみを表しつつ、2022年への意欲を語るなかでは「チームメイト(ガスリー)を倒せるように」と語るなど、フォーミュラレースの僚友としての適切な“線引き”ができている角田。おそれ過ぎてはいないあたり、頼もしく感じられる。
2年目以降の飛躍にも自然と期待が膨らんでくるドライバーだ。
◆今年こその日本GP実現を願いつつ、「言い訳は通じない」2年目へ
今季2022年、アルファタウリは姉妹チームのレッドブル同様に、ホンダから“継承”されたかたちの「Red Bull Powertrains」のパワーユニット(PU)を搭載して戦う(ホンダの“サポート”は継続される)。ドライバーはガスリーと角田で変化なし。
「(レギュレーション変更により)大きくクルマが変わるので、明確な目標は設定しにくいですけど、(昨年の最終戦)アブダビGPのフィーリングで開幕戦を終えられれば、と思います。(シーズンオフという)ブランクもあるので、レース勘のような部分も含めてベストな状態で開幕を迎えられるように、オフのあいだも頑張っていきたいです」
復活予定の日本GP(10月9日決勝、鈴鹿サーキット)についても、角田は強い思いを語る。
「去年いちばん楽しみにしていたGPがキャンセルになってしまい、残念でした。日本のファンのみなさんの前で走るのは夢でしたからね。(2012年の日本GPで)小林可夢偉選手が3位表彰台を獲ったとき、その場にいましたし、憧れました。自分もそうしたいと思っていましたので、本当に残念でした。ドライビングという意味でも鈴鹿は楽しいコース。今年こそ走れることを願っています」
そして2年目には、より良い結果と内容が求められることも角田は強く自覚している。
「もうルーキーイヤーではないので、言い訳は通じません。結果を求めて、毎戦毎戦、死に物狂いで戦っていきたいと思います。クルマの持っているパフォーマンスを毎戦、最大限に引き出していきたい。みなさん、応援よろしくお願いします」
2022年のF1は3月20日決勝のバーレーンGPで開幕する予定となっている(全23戦の予定)。