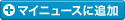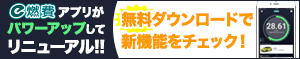日産はインフィニティ『QX60』をフルモデルチェンジ、秋より北米で発売を開始すると発表した。
◆タフさが欲しい
インフィニティ事業本部商品戦略・企画部所長のエリック・リゴー氏は先代QX60について、「全世界で40万台以上を売り上げ、我々の期待を大きく上回ったクルマ。従ってこのモデルチェンジは非常に大きなプレッシャーになった」という。そこでデザイナーには、「もっと力強さを表現したい。同時に素晴らしいファンクショナリティである広さは先代と同様に維持して欲しい」と、「非常に複雑なミッションを要望した」という。
その発言を受け、インフィニティ グローバルデザイン担当シニア・デザイン・ダイレクターの中村泰介氏は、「特にルーミネスとクオリティに関して、先代はプレミアムな3列のクロスオーバーとしてお客様に非常に受け入れられていた」と述べる一方、「ユーザーの話をよく聞くと、もう少しタフでいてほしい、もう少し守られている感じが欲しいということで、新型ではよりSUVの方向に振りつつ、スタンスが良くしっかりとした踏ん張り感じや、筋肉質な感じを表現。そしてシンプルでエレガントにまとまっていることを目指してデザインした」とコメント。
◆日本のDNAを感じさせながら
QX60のフロントは、「水平なベルトラインで、フードを高くデザイン。その結果、先代よりもノーズが上がっており、サイドから見ると立ったノーズが表現出来た」と中村氏。そうすることで、「グリルを少し大きくし、なおかつ色々な角度で見ても自信が感じられ、SUVらしいスタンスを作っている」と説明。
また、グリルのパターンは、「日本の折り紙や短冊状になっているところからインスパイア。ユニークな深さや3Dな感じを出そうとした。それがヘッドランプに上手く繋がっている」と話す。そのヘッドランプの光は、「テクノロジーの象徴なのでその表現の仕方としてデジタルピアノキーと呼んでいるデイライトランニングランプを採用。ひとつひとつキューブ状になっており、それが3つのユニットになっている」と述べる。その下には、クロームの表現があるが、これは、「着物パターンと呼んでおり、着物の襟が交差しているところをモチーフにした。そういった全体を日本のDNAが感じられるトーンでまとめている」と語る。
サイドビューは、「非常にリッチなボディセクションと強いショルダー、リアフェンダー周りでの筋肉質な感じにより、上手くSUVの強さを表現。アッパーキャビンを黒くしているのは、なるべくストリームラインに見えるようなシルエットと、強いボディのコンビネーションでこのクルマの特徴を表現している」と中村氏。
リアは、「フロントに呼応した幅の広いスタンスと、ぱっと見てホイールからホイールまでの幅をしっかりとボディのショルダーで表現。なおかつアッパーキャビンを緩やかに絞っており、その結果ショルダーがしっかりと後ろからも見えるようにした。それがこのクルマのスタンスを非常に安定させている」という。また、「クリーンで横長なデザインで、リアコンビランプのグラフィックも左右で繋ぎ、その中にはデジタルピアノキーがフロントと同じように入っている」とその特徴を説明した。
◆特徴的なインパネ周り
インテリアについて中村氏は、「ルーミネス感の表現は一番重要だった」という。また、「どうやってインフィニティらしい素材の扱い、テイラーの仕方が出来るもポイントだった」と述べる。
インストルメントパネルは非常に薄く横長に見せている。中村氏によると、「Aピラー to Aピラー(インパネの横方向)でまずキャビン全体の広さを表現。そして、ドライバーズシートに座ると腰下部分の囲まれ感、特に横方向に細く長いベンチレーションからセンターコンソールに向かっての片流れが、ドライバーセントリックな感じを表している」と説明。この表現方法は、「『QX55』と同じテーマだ」と中村氏はいう。
センターコンソール上にあるドライビングに必要なスイッチ類なども、「わかりやすくクラスタリング」。12.3インチのスクリーンがメーターとセンターにあるが、「その中でのテクノロジーの表現の仕方を、いかにフィジカルなクラフトマンシップと、デジタルなクラフトマンシップをどうすると一緒に出来るかにチャレンジした」と述べる。
具体的には、「3Dグラフィックの精度やバーチャルな深さ感、スクリーンの中に見える奥行き感を一生懸命表現しようとした。メーターモードを変えるとダイナミックに表情が変わり、クラシックモードではオーセンティックなダブルサークル、真ん中にクルマの情報が多く出るアドバンスモードもある」。
また特徴的なものとして、「仕立てとしてインストルメントパネルの上面にキルティングを配した。これは水の波紋をヒントに、波紋が重なってできる形をシートとインストルメントパネルの上面などに使っている」とコメント。
ベンチレーションがインストルメントパネルの薄さはベンチレーションが寄与しており、「黒いグラフィックで上下を分けることによって、より薄型でリッチに巻かれたパネル形状により、広さに貢献」。薄いインストルメントパネルは、「パフォーマンス感の表現で、そういったことがテクノロジーとデザインが上手く融合し、コンセプトを表現している」と中村氏。
センタークラスターの空調関係のスイッチは、フィジカルスイッチ(物理スイッチ)と静電スイッチが組み合わされ、「静電だけだと触ったか触っていないかがわからないので、触ったところが振動する、アクティブにリアクションする。従来のフィジカルなスイッチに代わる新しいデバイスとしてこのクルマから搭載している」と話す。
セカンドシートは、グレードによって左右が分かれ、真ん中にセンターコンソールが配されるキャプテンシートが選べる。デザインとしては、「それぞれのシートで機能が違うので、全く同じには出来ないが、可能な限り1列目と同じに見えるような仕立てにしている。キルティングやパーコレーション、パイピングの入れ方、お客様が触る色々な素材、レイアウトや構成などからもフロントと同じように作っている」と述べた。
エリック氏は、このキャプテンシートについて、「ビジネスクラスの感覚を味わってもらうという観点からデザイン。従って乗車人数は一人減るが、それだけ広さを感じることが出来る。また操作系も全て自分の手の届く所に配置。例えばベンチレーションの操作やUSBポートもある」とし、「乗客に対して目を向けることがQX60の特徴だ。全ての乗客をVIPのようにおもてなしをするということがこのモデルのコンセプトだ」とコメントした。
◆日本への導入は…
さて、今回搭載されるパワートレインは、V型6気筒3.5リットルで、マイルドハイブリッドなどは採用されなかった。その点についてエリック氏は、「もちろんより慎重に真剣に考えた」という。そして、「現在のパワートレインが、率直にいってアメリカ市場においては最良のパワートレインだと認識し、2021年の段階で市場から最も求められているものだ」と選択に間違いがないことを強調。一方、来年前半に導入される中国では、「このクルマは現地製造になり、パワートレインは異なってくるだろう」とコメント。
つまり、「市場ごとに調整しながらアプローチする。電動化についても今後どのようにしていくかは現段階では発表できないが、もちろん検討はしている」と述べ、「電動化のスピードが市場においてどのように展開されていくか、また、お客様が我々に何を望んでいるのかにもかかっている。もちろん市場での興味は高まっているとは思うが、現在アメリカにおいては、日本のラグジュアリーブランドもハイブリッドもラインナップされているが、お客様の大半が通常の電動化ではないエンジンを求めている」と語る。
日本での販売予定に関しては、「インフィニティにとって日本は不可欠だ。このモデルは日本でデザイン、R&Dも神奈川県から生まれ、そしてインフィニティ本社は横浜だ。つまりブランドそのもののルーツは日本にある」と成り立ちを説明。しかしながら、「日本で売るかどうかはまた別の問題だ。まだ結論は出ていないが、常に調査はしている」とわずかだが可能性も示唆。さらに、インフィニティブランドは日本では売られていないが、「調査を行った結果、日本では既に有名で、高級感があると評価は高い。それは我々にとって非常に良いことだ」と語った。