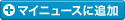![[コラム・車載用音響機材変遷史]第7回 2000年代に吹き始めた、「ハイエンド・カーオーディオ」への“向かい風”とは…。(画像はイメージ)。Photo by photoAC](https://image.e-nenpi.com/article_images/202508/399460/2131976.jpg)
クルマの中での音楽の聴かれ方の移り変わりを振り返っている当連載。音楽を持ち運ぶメディアの変遷とともに車載用音響機材の形も変化してきたわけだが、今回は2000年代に吹き始めた「ハイエンド・カーオーディオ」への“向かい風”について回顧する。
◆2000年代の中頃より、本格システムの構築がしづらくなり始める。原因となったのは…さて、70年代の半ばに音楽が持ち運ばれるメディアがカセットテープとなることで「カーステレオ」のブームが起こり、メディアがCDへと変わった90年代には「カーオーディオブーム」が起きたわけだが、実をいうと2000年代の後半へと差し掛かった頃に、カーオーディオブームに“向かい風”が吹き始めた。
その頃になると、ハイエンドカーオーディオシステムが組みにくくなり始めたのだ。
というのも2000年代に入った頃のブームの中では、本格システムは以下のようにして構築された。ハイエンドメインユニットを核として、そこに外部パワーアンプが組み合わされ、高級スピーカーがドライブされた。
なおハイエンドメインユニットはシステムの中で、ソースユニットとサウンドプロセッサーの役目を負った。CDに収められている音楽情報を高精度に読み取り、それを内蔵されている、または別体化されている高機能なDSPにて制御し、そしてそのピュアな信号が外部パワーアンプへと送られて増幅される。そうして高級スピーカーが鳴らされていた。
◆“DIN規格”ではない純正メインユニットが増え、市販品への交換が難しくなり…ところが2000年代には徐々に、その形を取るのが難しくなり始めていく。そうさせた大きな要因は2つあった。1つは「メインユニットが交換しづらい車種が増え始めたこと」で、もう1つは「AV一体型ナビが普及してきたこと」だ。
先述したとおり、カーオーディオシステムを本格化させようと思ったときにはまず、メインユニットが交換されることとなる。ところが2000年代の中頃には、いわゆる「DIN規格」ではない異形の純正メインユニットが増えてくる。
つまり、メインユニット交換を前提としない車種が増えてきたのだ。そしてそれらはセンタークラスターパネルと一体化していることが多く、取り外すことがそもそも難しい。また取り外せたとしても、そこにDIN規格の市販メインユニットを無加工ですっきりと収められない。
さらには、オーディオ以外の機能を背負っている場合も少なくなかった。例えばエアコンのスイッチも一体化している場合があり、そうであるとこれを外すとエアコンが使えなくなる。
◆「カーナビ」を付けると本格システムの構築がしづらくなり、入門者が徐々に減少…そして90年代に「カーナビ」が登場し、2000年代にはこれが相当に普及していく。で、カーナビはオーディオメインユニットの役目も負うこととなるのだが、音響機器として高性能な「AV一体型ナビ」はなかなか出現しなかった。ナビメカはノイズの発生源とも成るので、ハイエンドメインユニット化が難しかったからだ。
なので高音質システムを組もうとするときには1DINサイズのハイエンドメインユニットを使うことが条件となり続けていたのだが、AV一体型ナビを導入するとセンタークラスターパネルにハイエンドメインユニットを装着するスペースがなくなってしまう……。
それでも愛好家の多くは、なんとかしてハイエンドメインユニットを愛車に組み込んだ。しかしそれがハードルとなり新規の愛好家が増えにくくなっていく。
こうして徐々に、ハイエンドカーオーディオという趣味は、マニアだけのものという色彩が濃くなっていく……。
今回は以上だ。次回はその状況を覆そうとする新たな潮流について説明していく。お楽しみに。