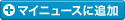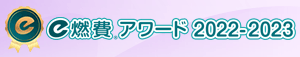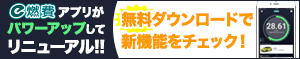カーオーディオユニットを自分で取り付けてみたいと考えているドライバーに向けて、そのコツを解説している当コーナー。前回からは「サブウーファーボックス」の自作方法を解説している。今回は、「設計」における注意事項を説明する。
さて、「サブウーファーボックス」を作るにあたっては、まずは「設計」がポイントとなる。で、「設計」においてはカタログ等に記載されている「推奨容量」に合わせて大きさを決める必要がある。その範囲の中で少々大きめに「設計」するのがコツとなると前回の記事にて説明した。
そうして容量を決めたら、その容量を確保できるように計算しながら形を決めていこう。
さて「設計」する際にはまず、「サブウーファーユニット」の取り付け面の大きさを考えよう。その際には、使用する「ユニットサブウーファー」の取り付け穴口径を確保できることはもちろん、「ユニットサブウーファー」のフレームの大きさをカバーできる大きさを確保する必要がある。なお、細長い「ボックス」にしたいと思っても、取り付け面は「ユニットサブウーファー」が余裕を持って取り付けられる大きさを確保したい。そうした方が取り付け面の強度を担保しやすくなる。
そして続いて問題となるのは、「ボックス」の厚みだ。まず、使用する「ユニットサブウーファーの奥行き寸法よりも厚みを取ることがマストとなるが、「ボックス」の厚みをほどほどにしたい場合でもある程度は厚みを持たせた方が良い。というのも厚みが短いと「ユニットサブウーファー」の裏側から放たれる音エネルギー(背圧)があまり減衰せずに「ユニットサブウーファー」に戻ってくる。となるとそのエネルギーが振動板の動きにストレスを与えてしまう。これはあまり良いことではない。
ちなみにいうと、プロが作る場合には中に吸音材を入れるなどして厚みが少なくても背圧の影響を少なくする工夫が施されたりもする。しかしそういった工夫を実行するには経験とノウハウが必要となる。なので自作する場合には、厚みが少なくなりすぎないようにした方がベターだ。
またシンプルな直方体ではなく台形的な形にすると、箱の内部での背圧の反射の影響が複雑化するのでより良い低音を奏でやすくなる。容量の計算は難しくなるが、多少複雑な形で「設計」した方が良い。参考にしてほしい。
今回は、ここまでとさせていただく。次回はこの後の工程におけるポイントを説明していく。お楽しみに。